思想史から見た日本の近代と中国の近代:韓東育先生に聞く(上)

(日文研にて、伊東貴之教授と談笑する様子)
韓東育、東京大学大学院にて博士(学術)取得。専門は日本史、東アジア史 、東アジアの国際関係史。中国東北師範大学副学長を経て、現在、同大学教育部人文社会科学重点研究拠点「世界文明史研究センター」主任、東アジア研究院院長。中国国務院学位委員会世界史学科評議組召集人、教育部高等教育指導委員会副主任委員、国家社会科学基金審査委員を務める。東京大学客員研究員、日本学術振興会外国人特別研究員、九州大学客員教授 、台湾大学訪問学者、国際日本文化研究センター外国人研究員などを歴任。中国史学会副会長、中国日本史学会会長ほか、学会・編集委員を多数務める。主著に『從「脫儒」到「脫亞」――日本近世以來「去中心化」之思想過程』(台湾大学出版会、2009年)、『從「請封」到「自封」:日本中世以來「自中心化」之行動過程』(台湾大学出版会、2016年)、『從「道理」到「物理」──日本近世以來「化道為術」之格致過程』(台湾大学高研院、2020年)などがある。
問1:日本思想史、特に近世思想をご研究の出発点にされた経緯について、お聞かせください。
韓:私はもともと中国古代思想史の研究をしており、専門としては先秦期の歴史、とりわけ先秦時代の思想史を中心に据えておりました。ただ、授業の都合で、魏晋玄学ないし宋明理学を含め、中国思想史全盤に対して幅広い興味を持つようになったのです。日本に留学した当初、実は陽明学の研究を深めるつもりでした。陽明学は日本で深い影響力を及ぼし、その思想水脈は明治維新に大いに繋がっていると言われているので、さらに掘り下げて研究する意義があると考えていたのです。ところが、東京大学において黒住真先生の講義を拝聴したことは、私の研究の方向が転換する大きなきっかけが生じました。黒住先生は江戸時代の思想史を専門とされており、講義では江戸時代のさまざまな学派、とりわけ経世学派についてご紹介くださいました。経世学派は朱子学に対する目線が非常に厳しいと言われて、この点に私は深く惹かれました。なぜ「実学」を掲げて、「実学」とも自家標榜した朱子学を批判するのか?私の中に強い好奇心が湧いてきました。
当時、黒住先生から丸山眞男の『日本政治思想史研究』を読むよう勧められました。この書物は、私にとってまさに革命的な閃きをもたらしました。丸山の綿密なテキスト分析によりますと、経世学派は朱子学が提唱している「理」のような宇宙を貫く絶対的法則に拘らず、より実践的で、現実の政治や社会統治に役に立つような学問を志向していたとのことです。これは、私が長年漠然と抱きつつ、うまく表現できない問題意識そのものでありました。
私は当時、新百合ヶ丘に住んでいました。ある日、家族と公園に出かけた折に、その本を持参し、子どもが公園で遊ぶのを眺めながら読んでいました。荻生徂徠に関する箇所を読んでいたとき、不意に胸が熱くなり、思わず顔がほころびました。心の底から「これだ」と感じたのです。長く胸の奥でくすぶっていた思索が、ようやく輪郭を持って現れたような気がして、嬉しさのあまり、思わず土手から転げ落ちてしまったほどでした。
ご存知の通り、経世学派の思想的特徴は、抽象的な「道」から実務的な「術」への転化にあり、国家の統治や民生の改善を儒学の核心的課題とするパラダイム転換であるとされています。彼らは孔子の再解釈にも努め、孔子を「理」や「気」といった形而上学を論じる賢人としてではなく、現実社会に目を向け、人々の生活に深い関心を寄せた聖人として捉え直したのです。このような思想的動向は、ちょうど江戸中期に商業経済が活発化し、社会階層が大きく変動しつつあったという時代背景の中で生まれてきたのです。士農工商の秩序が揺らぎ、士や農が周縁化される一方で、商人や手工業者が社会の主たる担い手として台頭していきました。こうした時代にあって、経世学派の思想は、きわめて実用的であり、また将来性に富むものとして映ります。
こうした経緯により、私は当初予定していた陽明学の研究をいったん脇に置き、経世学派、ひいては江戸思想の世界へと歩を進めることになったのです。
問2:ご研究を拝見して、丸山眞男とは異なる思想的な立場や視座を感じました。先生はどのような問題意識から、そのようなアプローチを取られたのでしょうか。
韓:私が法家思想の影響を改めて見直すようになったきっかけは、荻生徂徠の読解でした。徂徠は自身の論理を構築していく過程で、弟子である宇佐美灊水が「蓋し読荀子の成るは韓非子の前にあり」と言ったとおり、まず『荀子』と向き合い、そこから『韓非子』の受容へと進んでいくかのような思想的な軌跡でした。徂徠によるこうしたアプローチは、私にとってきわめて示唆に富むもので、それから夢中で読み進め、『荻生徂徠全集』を通読しました。その中で私が気づいたのは、徂徠思想の重要な柱の一つが、他でもなく、韓非が主張している、いわゆる「人情」論であるということでした。
韓非の説く「人情」とは、孟子のいう「性善」でも、荀子の「性悪」でもありません。つまり、人間が道徳教育を受け、その論理で物事を考える以前に、ごく自然に抱く「好むもの・嫌うもの」――そうした自然な情動の在り方を指しています。ここで重要なのは、韓非が価値判断を下しているのではなく、あくまで事実を描写しているという点です。人間は何を好み、何を嫌うのか。その自然な傾向に基づいて、政治的な操作が可能になる。たとえば、賞罰の制度はこの「人情」の理解を前提に築かれていくのです。この発見は、私にとって非常に大きな転換点となりました。私はかつて、韓非は「性悪説」の代表的な論者だと誤って理解していました。しかし、解読を進めるうちに、彼が語っていたのは「人性」ではなく「人情」であったことに徐々に気づいていったのです。この点は、中国の学界においても長らく誤解されてきた部分です。そしてまさに、荻生徂徠はこの「人情」に立脚して朱子学を批判していきます。朱熹の思想的源流は、周知のとおり孟子に遡ることができるため、徂徠はその系譜をたどるなかで、ついには孔子にまで疑念を抱くようになっていきました。
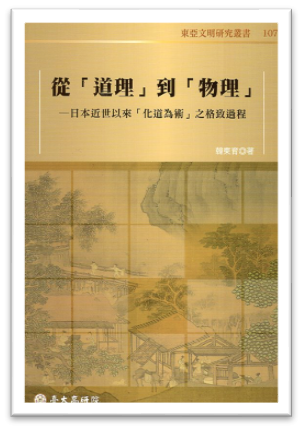
(韓東育:『從「道理」到「物理」──日本近世以來「化道為術」之格致過程』台湾大学高研院、2020年)
もっとも、徂徠自身はなお法家思想と一定の距離を保っていましたが、弟子太宰春台をはじめとする門人たちは、さらに一歩踏み込み、儒と法の架け橋である荀子の人間中心的な思想を強調し、「天」という超越的存在への想像から一層の脱却を図る立場をとりました。孫弟子の海保青陵らは、韓非・荀子・老子を網羅的かつ統合的に受容し、「道」を国家統治の技術として具象化し、賞罰制度の中に「理」の哲学を導入したのです。このように、抽象的な形而上学を社会管理の実践へと「翻訳」する思考様式は、まさに江戸中期における商業経済の隆盛と、社会階層の流動化という時代状況と響き合うものでした。
荻生徂徠を読んだ後、私は丸山眞男を読み返し、さまざまな啓発を受けました。しかしながら、丸山による徂徠理解には、やはり限界があることに次第に気づかされました。具体的には、丸山は西洋政治思想の枠組みをあらかじめ前提とし、そこに徂徠を当てはめようとしたのです。もちろん、その視点もきわめて示唆に富んでいますが、徂徠自身の思考とは、やや齟齬があることは否めないように思われます。
丸山は、江戸時代の中後期を論じるなかで、当時の日本において萌芽しつつあった「自発的資本主義」の存在を高く評価しました。彼によれば、たとえ明治維新が日本近代資本主義の出発点であるにせよ、その準備過程は150年ほど前にまで遡らなければならないというのです。そしてこの過程を理解するためには、荻生徂徠と経世学派の再検討が不可欠であるとされます。
しかしながら、丸山は「近代化論」の忠実な信奉者である以上、西欧中心主義的な視点からは簡単には脱却できなかったでしょう。したがって、近代化の起源を日本内部に求めようとする彼の試みには、どうしても西洋という鏡を通して日本の思想を見つめるという傾向が見られます。その結果、荀子や韓非子といった中国古典思想の影響は視野からこぼれ落ち、場合によっては、意図せざるかたちで抹消されてしまっているのです。
丸山にとっては、日本思想史の中にも、“日本版ホッブズ”や“日本のマキャヴェッリ”といった対応物が、あるべくして存在していたのかもしれません。しかしながら、そのような見方は「後ろから歴史を見る」目線に基づくものであり、本来は慎重に扱うべきものです。徂徠を論じる際の丸山のアプローチも、まさにこの「後ろから歴史を見る」視点に立っていたといえるでしょう。そのため、丸山が設定した「思想触媒」はあくまで西洋思想であり、中国古典思想の影響は見落とされてしまいました――徂徠の思考の源泉にあったのは、むしろ荀子や韓非といった後者の系譜だったのではないか。私は研究を通じて、まさにこの点に気づき、強く確信するに至ったのです。
問3:「新法家」という概念には、先生の独自の問題意識が込められているように思いますが、この発想はどのような背景や問いから生まれてきたのでしょうか?
韓:私が言う「新法家」とは、いわゆる伝統的な意味での法家ではありません。むしろ、荀子や韓非の思想を媒介とし、日本の儒学者たちによって展開された、実践的かつ現実主義的な思想体系を指しています。
まず第一に、「新」とは時代の「新」です。
「徂徠派経世学」は十七世紀に始まり、海保青陵に至るまで、約1世紀余りを経て形成された思想です。当時の日本は封建制度から中央集権体制へと移行する過渡期であり、両体制が並存する時代でもありました。しかし、中国における同様の変化(東周から漢の武帝にかけて)と比較すると、そこには約二千年という時間差があります。応急的で選択の余地が乏しかった当時の中国の政治家に対して、江戸時代の日本の思想家たちは、二千年にわたる歴史的経験を参照しつつ、時代に最も適合する理論を選び取ることができたと考えられます。
第二に、「新」とは原理の「新」です。
韓非子における誤読された「性悪」論に代わり、本質的な「人情」論が打ち出されたことで、法家の政治学的原理は、初めて徂徠学派によって復元されたのです。皮肉なことに、それとは対照的に、前近代の中国では、そういった法家思想の原理は歴史の流れの中で次第に倫理思想や価値判断に圧倒され、「人情」の重要性は徐々に失われていきました。しかしその一方で、この「人情」への関心は、むしろ日本においてこそ受け継がれていったのです。まさにそこに、この思想の「新しさ」の意義があるのです。
第三に、「新」とは役割の「新」です。
「君臣市道」とは言うものの、原始法家はこれを主に認識論上で認めるにとどまり、実践のレベルではむしろ「抑商」論を提唱していました。それに対して、特に海保青陵においては、「商売」の原則が徹底して展開されています。そもそも原始法家における認識論ですら、「利益原則」に反対し、独尊的地位を得た儒家によって批判されてきました。こうして、旧来の法家思想は新たな社会を切り開く契機とはなりえず、その後の二千年余りの歴史の中で、法家は支配層の権力闘争の道具として密かに用いられるのみとなり、公的な言説の場からは姿を消していきました。それに対して、「徂徠派経世学」では、商品経済が急速に発展する中で、「商売関係があらゆる領域に及ぶ」という現実を直視し、その問題をめぐって真剣な議論が交わされました。そもそも「徂徠派経世学」は、江戸時代の町人など中層民衆の間で高まっていた「利」への意識の勃興を、武士層の側から受け止め、理論化したものと捉えることもできるでしょう。
そして、西洋の近代文明が洪水のように日本へ押し寄せたとき、近代化の原理と類似性をもち、かつ江戸時代の社会的現実を的確に反映していた「徂徠派経世学」は、新しい時代に対応しうる思想的可能性を蓄積していたのです。この意味において、「徂徠派経世学」は、明治以後の日本における社会的転換が迅速に進んだ背景の一つを、思想の側から説明する鍵を提供しているのではないかと考えられます。
(下に続く)


