思想史から見た日本の近代と中国の近代:韓東育先生に聞く(下)
問4:近代国家というテーマに触れていただきましたが、思想史的な視点から見た場合、日本と中国の近代化にはどのような違いがあると捉えていらっしゃいますか。
韓:日本の明治維新がこれほど印象的だったのは、やはり「全面的な西洋化」に踏み切ったからだと思います。鹿鳴館に象徴されるように、日本は食べ物や日常の作法から、都市の景観や街並みに至るまで、西洋の都市文化やライフスタイルを徹底的に模倣していきました。こうした極端とも言える変化の背後には、中国やアジア諸国のように植民地化および半植民地化されることへの、強い危機感があったのではないでしょうか。「相手を追い越すには、まず相手に変わろう」という原理が日本の近代化を方向づけたのに対して、中国の近代化は、「枠組みを維持したまま外来事物を取り入れる」という姿勢にとどまっていたように思います。
たとえば清朝末期には、洋務運動によって軍事や教育制度が大きく見直され、西洋の科学技術も広く導入されました。しかしながら、政治制度や社会構造、人々のライフスタイルに関しては、ほとんど変化が見られませんでした。それに対して日本では、いわゆる「東洋道徳・西洋芸術」(佐久間象山)という考え方があり、しばしば「和魂洋才」的な折衷思想として捉えられがちですが、実はそう単純なものではありません。ここで言う「芸術」――つまり西洋の諸学問の導入は、単なる技術的な模倣にとどまらず、その背後にある「体」、すなわち政治改革や知的枠組みそのものの転換までをも含んでいました。この点において、日本の近代化は、中国の「中体西用」とは本質的に異なっていたのです。
とはいえ、明治維新の時代においても、日本が伝統をすべて捨て去ろうとしたわけではありません。特に列強の圧力が強まる中で、国家の求心力をいかに維持し、統合を図るかは大きな課題でした。そうした状況において、朱子学が説く「権威と権力の一体化」は、理論的な支えとして機能したのです。その結果、日本は近代国家としての体制整備を比較的早く進めることができ、清やロシアとの戦争にも勝利を収めるに至ったのだと思います。
この点について丸山眞男が明確に指摘しているわけではありませんが、彼が荻生徂徠の研究を通じて、そこに一定の問題意識を抱いていたことは確かだと思われます。たとえば丸山は、日本の伝統的な政治構造には「権威と権力の分離」が存在していたと述べています。しかし、朱子学が政治的に利用された結果として、「権威と権力の一体化」が進み、そこに全体主義的、さらには超国家主義的な傾向が準備されていったのではないでしょうか。実際、津田左右吉が東京帝国大学の講義の中で、天皇が軍政的指導者であることを批判するような発言をした際、「非国民だ」と学生から罵倒されたという有名な逸話があります。これはまさに、朱子学が「作られた伝統」として再構成されることによって、本来の日本的な政治構造が覆い隠され、軍国主義的拡張を可能にする思想的土壌となってしまったことを象徴する事例です。そして、江戸時代に批判されてしまった朱子学思想がなぜ明治に入ってからかえって復権したのか、と。丸山が徂徠を論じる中で掘り下げようとしたのは、まさにこうした論点だったと思いますし、そして戦争の責任を他者に押し付けようとする潜在的な意思があるかどうか別にして、戦後の朱子学批判は、簡単に受け止めることができないのではないかと考え直すべきだと思います。
問5:日中両国の近代化に対する知識人の態度の違いは、思想形成にどのような差異をもたらしたのでしょうか。とりわけ、丸山眞男と李沢厚の1989年3月の対面・対話は、その違いを象徴的に示すものだったと考えられます。
韓:この対話記録は、東京女子大学の丸山眞男研究センターに保存されており、全文も丁寧に整理されていました。私はかねてより、丸山眞男と李沢厚という、日中それぞれの思想界を代表する第一人者が一度でも対面していたならば、それは東アジア思想史においてきわめて画期的な意味をもつ出来事になっていただろう、という想いを抱いてきました。ですから、この記録を実際に目にしたときには非常に感慨深く、読み進める中で、著作集の中では見えてこなかった丸山の「閃き」の瞬間が、この対話のなかにこそ確かに刻まれていたことに、深い驚きを覚えました。
それに、李沢厚による日本社会への直感的な理解は、きわめて鋭いものがあります。李は、日中両国においては、共通点よりもむしろ相違点のほうが本質的に重要であると述べており、丸山もこれに深く頷いていました。なかでも李が注目したのは、日本における人間関係倫理の基盤としての「忠」と「孝」が、中国のそれとは根本的に異なる構造を持っているという点です。具体的には、日本では父親が子育てにあまり関与しないため、「孝」は父と子の理性的関係というより、主に母と子の感情的関係に基づいて形成されます、と。一方で、社会的関係の中心には君臣関係があり、「忠」は男性同士の規範として機能しています。つまり、孝の対象は母、忠の対象は主君――両者は交わらず、それぞれ異なる次元で機能しているのです。その結果、日本人にとっては、主君のために命を捧げることと、親孝行を果たすことが矛盾しないという感覚が成立するわけです。
それに対して、中国において「孝」は、まず父と子の関係として捉えられ、すべての人間関係における倫理の出発点とされています。「忠」はその延長線上に位置づけられており、家族内の倫理がそのまま社会的文脈に拡張されるかたちで、倫理構造は連続的に展開されます。李沢厚によれば、それは母系社会が長く存続していた日本と異なる中国父系社会の目立った特徴ではないかという。しかし、「忠」と「孝」が対立する状況――たとえば、非道的な主君のために命を捧げなければならないような場面では、中国人は「孝」を優先する傾向がよく見られます。こうした基本的な倫理観のあり方における日中間の明確かつ根本的な違いは、後の近代国民国家の形成においても、少なからぬ影響を及ぼしたと、李も丸山も認めていたわけです。
もっとも、李と丸山とのあいだには、根本的な立場の違いも見受けられる。とくに、「救亡」と「啓蒙」をめぐる考え方において、両者の見解はやや分かれていました。周知のとおり、李沢厚は「救亡が啓蒙を圧倒してきた」という論点で知られています。彼によれば、中国の五四運動は、当初こそ「民主」と「科学」を掲げた啓蒙的運動でしたが、抗日戦争の勃発によって、その理念は一時的に後景に退き、「国家の存亡をかけた救亡」が最優先課題として浮上したということです。つまり、非常時においては、たとえ一時的に独裁政権に身を預けるとしても、まず国家の存続を確保することが優先されるという判断が下されたというのである。ただし、ここで重要なのは、李がこのような歴史的展開を是認しているわけではありません。この発言は、改革開放が進んでいた1980年代において、大きな反響を呼びました。鄧小平による経済改革が加速するなかで、思想的な領域でも「科学と民主」という五四運動以来のスローガンが再び前面に掲げられ、「中断された啓蒙をいかに継続するか」という問題意識が、多くの知識人のあいだで共有されるようになっていきます。
しかし、こうした状況に対して、丸山眞男はきわめて慎重な立場を取っていました。丸山にとって「啓蒙」とは、時勢や国難の名のもとに一時的に棚上げされるような可変的な課題ではなく、知識人が不断に担い続けるべき倫理的責務でありました。その背景には、昭和期の日本において、知識人自身が啓蒙の営みを放棄し、進んで反理性・反近代の潮流に身を投じていった歴史への痛切な反省があります。そうした精神的退廃が、結果として国家の破局をもたらしたという体験が、丸山の思想の基底に強く刻まれていたのです。
しかし、このような丸山の視点とは異なり、李沢厚が論じたのは、中国近代における時代の変遷と、それに伴って変化する啓蒙の位置づけの問題でありました。李の時代区分によれば、中国近代は、「啓蒙による国民の覚醒 → 国家の存亡への直面 → 啓蒙に優先するかたちでの救亡 → 苦難を経た国家の再生 → 国民による啓蒙への回帰」という一連の連続した歴史段階として捉えられます。したがって、歴史が倒錯や反動を経て本来の軌道へと回帰したときにこそ、日中それぞれの思想界の頂点とも言うべき知識人による対話は、両国の近代化に関する誤読や複雑な絡まりを解きほぐすうえで、意義ある鍵を提示しうるのではないだろうか。
問6:近代化のプロセスは、それぞれの国が異なる道を歩んできました。これから人・モノ・資本の流動性がますます高まる中で、東アジアはどのように、これまでの歴史的秩序や制度の慣性に影響されながら、独自の発展を遂げていくとお考えでしょうか。
韓:この問題に対する考察の出発点として、まず日文研の劉建輝氏が提唱する東アジア諸国が「支え合う200年」史観に注目する意義は大きいと感じます。劉氏によれば、中日韓を含む東アジア諸国は、過去200年にわたって西洋からもたらされた新たな価値体系と物質文明に、それぞれ異なるかたちで向き合いながら、その適応の過程で絶え間ない摩擦と衝突を経験してきました。この適応のプロセスは、当然ながら混乱や痛み、制度的・文化的停滞を伴うものでしたが、やがて東アジアの諸社会は、かろうじてではあるものの、協力、交易、そして文化的な相互理解へとたどり着いたといえるでしょう。
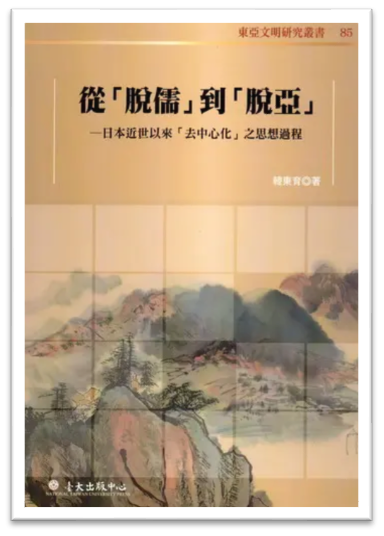
(韓東育:『從「道理」到「物理」──日本近世以來「化道為術」之格致過程』台湾大学高研院、2020年)
私自身は、このプロセスをより長期的な時間軸――すなわち500年という歴史的スパンの中で、連続的な変化として捉えています。遅くとも明清期において、日本が華夷秩序に挑戦した時点から、東アジアは単一の中心から中国と日本という二極的な構造へと移行しはじめていました。その狭間にある諸々の小国は、両大国の間で不断の駆け引きを強いられるようになったのです。こうした変化は、単なる地域的な勢力図の塗り替えにとどまらず、思想や認識の枠組みそのものの転換をも意味していました。
ここで述べている「500年」という時間軸には、先に言及した近代化の200年も含まれています。私が指摘したいのは、東アジアの秩序の崩壊は、いわゆる「黒船来航」以後に突然始まったのではなく、それ以前からすでに進行していたという点です。もともと中国を中心とするドミナントな華夷秩序は、明清期以降、徐々にその求心力を失い、従来の中華中心的な価値構造は、各地域における「ローカルな中心」によって置き換えられつつありました。「理一分殊」にしても、「月印万川」にしても、日本は日本式の華夷秩序を構築し、朝鮮やベトナムもまた、それぞれ「小中華」「小中国」として自らを中心と位置づけようとしたのです。その結果、東アジアは一極的な構造から多中心的な秩序へと移行しつつありました。西洋の登場は、こうした構造変動を加速させはしたものの、その発端となったわけではありません。
したがって、現代において東アジア諸国が中国に対して一定の距離を保とうとする姿勢は、単なる経済的利益や地政学的な利害にとどまらず、前近代秩序への回帰に対する無意識的な警戒心の表れでもあると考えられます。たとえば、朴槿恵政権期に提起された「アジア・パラドックス」という概念――すなわち、政治的にはアメリカに依存しながら、経済的には中国との関係を深化させるという構図――は、まさにそうした複雑で矛盾をはらんだ心理的態度を象徴的に示すものでしょう。
こうした背景を踏まえるならば、中国の知識人が近隣諸国との関係を再構築しようとする際には、何よりもまず、相手国の歴史的記憶や心理的背景に対する真摯な理解が不可欠です。近代の国際法的論理が「平等」という理念をその核心に据えているのに対し、伝統的な華夷秩序は「温情」と呼ばれる倫理的相互扶助の原理を備えていました。もしこの二つの原理――すなわち制度的平等と倫理的温情――が相互に補完されうるならば、東アジアにおいては、従来とは異なる新たな秩序の地平が開かれる可能性があるでしょう。ただし、文化的伝統に根ざした「温情」は、もはや他者を従わせるための道徳的正当性の根拠とはなり得ないです。真に必要なのは、相互の平等を尊重し、道理をわきまえ、他者を見下さない姿勢です。「道を得る者は助け多く、道を失う者は助け寡し」――まさにこの言葉が、いま新たな文脈において問われているのではないでしょうか。
私たち研究者が目指すべきは、もはや自国中心主義やナショナリズムにとらわれ、立場によって他者を押さえつけることではなく、むしろ冷静に現実を見つめ直し、相互理解の可能性を探ることではないでしょうか。東アジア諸国は、過去200年にわたり、それぞれが西洋の近代的な体系と向き合いながら、摩擦と調整を繰り返しつつ、徐々にグローバルな世界システムへと組み込まれていくプロセスを歩んできました。これは、文明の歴史的な流れの一部であり、過度にイデオロギー化された言説によって単純化されるべきものではありません。そして、現在の不安定な国際情勢の中で、国家主義や地政学的対立を超えて、文化・物質・精神の次元における真の往還が始まりつつあるとも考えられます。そのとき、私たちは東アジアの地から、これまでにない新たな価値や思想の萌芽が生まれる瞬間に立ち会うことになるかもしれません。
(聞き手:周雨霏〔日文研・上廣国際日本学研究部門〕)
――完――


